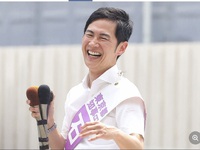2016年01月31日
赤信号の消費世界
ヒット商品応援団日記No635(毎週更新) 2016.1.31.
昨年から気がかりであった「消費の動向」、さらに小売現場の売り上げ数字がほぼ出そろった。前者については家計調査(二人以上の世帯)平成27年(2015年)12月の速報値で、後者は百貨店協会と日本SC協会による昨年12月度の売り上げ数字である。
まず、家計調査の消費支出(前年同月比)である。
10月▲2.4%
11月▲2.9%
12月▲4.4%
ちなみに勤労者世帯における実収入は以下となっている。
10月▲0.6%
11月▲1.4%
12月▲2.7%
そして、小売現場であるが、全国百貨店の売り上げにおいては
10月+4.2%
11月▲2.7%
12月+0.1%
SC(ショッピングセンター)においては
10月+2.8%
11月▲2.9%
12月▲0.1%
こうした赤信号の消費を踏まえてであると思うが、10~12月のGDPの予測が民間の調査機関12社から発表されている。NHKのまとめによると、物価の変動を除いた実質で前の3か月と比べて▲0.1%から▲0.7%。年率では、▲0.5%から▲2.8%と予測していると。ちなみにみずほ総研は前期比▲0.4%(年率▲1.5%)、日本総研では前期比▲0.3%(年率▲1.4%)といったところであるが、各社消費が大きくマイナスになっていると指摘をしている。GDPに占める消費が60%を超えている状況であれば当然と言えよう。
ところで、昨年夏のブログには「消費後退の夏」というタイトルでお盆休み旅行の特徴について次のように書いた。
『JTBによれば今年の夏の旅行の特徴となっているのが「観劇、イベント参加、スポーツ観戦」(1.1%増)の増加が目立つという。また、利用交通機関では、レンタカーを含む乗用車の利用が5.6ポイント増で約7割に拡大。JR新幹線は1.4ポイント減の13.4%に縮小したと。今年の夏の消費を見ていくと、メリハリ消費から後退した感が強い。昨年の消費増税によってワンコインランチや激安・デカ盛りといったデフレ型消費が再燃したが、ここにきてそうした消費が加速しそうである。』
年末年始の旅行も休暇の期間が短いこともあるが、同じような傾向であった。こうした消費の後退傾向は上記の数字が物の見事に表している。何回となく書いてきたので同じことを書こうとは思わないが、収入が増えない限り消費も増えないことは当然である。百貨店については訪日外国人による消費によってかろうじてプラスにはなっているが、その内訳としては東京、京都、大阪、といった都市部の百貨店だけで地方都市は軒並みマイナス状態である。そして、逆な見方をするならば、日本人による消費は極めて悪いということでもある。そして、気がかりなのはSCにおける売り上げ低迷である。周知のように商圏内の特徴に合わせて専門店を編集するので、消費増税による顧客変化にもそれなりに自在に対応することが可能な業態である。この業態がマイナス傾向を見せることはかなりの赤信号であると理解すべきである。
このブログを書いている最中に日銀のマイナス金利の発表があった。インフレ目標の期限を3度も先延ばし、国債だけでなく株式市場においても買い支えるという中でのマイナス金利の発表であるが、その主要目的は円安と株高である。この2つに関係する一部の関連業種にとっては意味あることかもしれないが、すでにEUでは行われており、さしたる効果がないことがわかっている。そして、「消費」という視点に立てば、原油価格の暴落が物価に及ぼす影響は極めて大きい。
例年であれば年頭の新聞各紙を斜め読みしてコメントするのが常であったが、今年は「混迷の年が始まる」とした。もちろん、内外ともに政治も経済も問題が絡み合って解くことが難しいことを表したが、国内経済、特に消費については昨年夏からすでに始まっている。
消費後退とはその心理が内側へと向くことである。より吟味して、より熟慮して、財布と相談しながら余計な消費はしないということである。さらに今年に入り、産廃業者からの廃棄商品横流し事件が起きたが、こうした内側に潜む「見えない世界」への疑念が不安を増幅させている。以前ブログにも書いたが、「顔の見える」関係からさらに内側へと向かい「心までもが見える」関係が求められることとなる。こうした内側に向く消費心理は慣れ親しんだ商品や店、安心の持てる商品や店に向かう消費である。結果、ブランドや老舗、場合によっては後継者不足で廃業した街場のお店の復活などが注目されることとなる。再び「安心コンセプト」を求める時代を迎えたということだ。(続く)
昨年から気がかりであった「消費の動向」、さらに小売現場の売り上げ数字がほぼ出そろった。前者については家計調査(二人以上の世帯)平成27年(2015年)12月の速報値で、後者は百貨店協会と日本SC協会による昨年12月度の売り上げ数字である。
まず、家計調査の消費支出(前年同月比)である。
10月▲2.4%
11月▲2.9%
12月▲4.4%
ちなみに勤労者世帯における実収入は以下となっている。
10月▲0.6%
11月▲1.4%
12月▲2.7%
そして、小売現場であるが、全国百貨店の売り上げにおいては
10月+4.2%
11月▲2.7%
12月+0.1%
SC(ショッピングセンター)においては
10月+2.8%
11月▲2.9%
12月▲0.1%
こうした赤信号の消費を踏まえてであると思うが、10~12月のGDPの予測が民間の調査機関12社から発表されている。NHKのまとめによると、物価の変動を除いた実質で前の3か月と比べて▲0.1%から▲0.7%。年率では、▲0.5%から▲2.8%と予測していると。ちなみにみずほ総研は前期比▲0.4%(年率▲1.5%)、日本総研では前期比▲0.3%(年率▲1.4%)といったところであるが、各社消費が大きくマイナスになっていると指摘をしている。GDPに占める消費が60%を超えている状況であれば当然と言えよう。
ところで、昨年夏のブログには「消費後退の夏」というタイトルでお盆休み旅行の特徴について次のように書いた。
『JTBによれば今年の夏の旅行の特徴となっているのが「観劇、イベント参加、スポーツ観戦」(1.1%増)の増加が目立つという。また、利用交通機関では、レンタカーを含む乗用車の利用が5.6ポイント増で約7割に拡大。JR新幹線は1.4ポイント減の13.4%に縮小したと。今年の夏の消費を見ていくと、メリハリ消費から後退した感が強い。昨年の消費増税によってワンコインランチや激安・デカ盛りといったデフレ型消費が再燃したが、ここにきてそうした消費が加速しそうである。』
年末年始の旅行も休暇の期間が短いこともあるが、同じような傾向であった。こうした消費の後退傾向は上記の数字が物の見事に表している。何回となく書いてきたので同じことを書こうとは思わないが、収入が増えない限り消費も増えないことは当然である。百貨店については訪日外国人による消費によってかろうじてプラスにはなっているが、その内訳としては東京、京都、大阪、といった都市部の百貨店だけで地方都市は軒並みマイナス状態である。そして、逆な見方をするならば、日本人による消費は極めて悪いということでもある。そして、気がかりなのはSCにおける売り上げ低迷である。周知のように商圏内の特徴に合わせて専門店を編集するので、消費増税による顧客変化にもそれなりに自在に対応することが可能な業態である。この業態がマイナス傾向を見せることはかなりの赤信号であると理解すべきである。
このブログを書いている最中に日銀のマイナス金利の発表があった。インフレ目標の期限を3度も先延ばし、国債だけでなく株式市場においても買い支えるという中でのマイナス金利の発表であるが、その主要目的は円安と株高である。この2つに関係する一部の関連業種にとっては意味あることかもしれないが、すでにEUでは行われており、さしたる効果がないことがわかっている。そして、「消費」という視点に立てば、原油価格の暴落が物価に及ぼす影響は極めて大きい。
例年であれば年頭の新聞各紙を斜め読みしてコメントするのが常であったが、今年は「混迷の年が始まる」とした。もちろん、内外ともに政治も経済も問題が絡み合って解くことが難しいことを表したが、国内経済、特に消費については昨年夏からすでに始まっている。
消費後退とはその心理が内側へと向くことである。より吟味して、より熟慮して、財布と相談しながら余計な消費はしないということである。さらに今年に入り、産廃業者からの廃棄商品横流し事件が起きたが、こうした内側に潜む「見えない世界」への疑念が不安を増幅させている。以前ブログにも書いたが、「顔の見える」関係からさらに内側へと向かい「心までもが見える」関係が求められることとなる。こうした内側に向く消費心理は慣れ親しんだ商品や店、安心の持てる商品や店に向かう消費である。結果、ブランドや老舗、場合によっては後継者不足で廃業した街場のお店の復活などが注目されることとなる。再び「安心コンセプト」を求める時代を迎えたということだ。(続く)
失われた30年nの意味
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
Posted by ヒット商品応援団 at 13:38│Comments(0)
│新市場創造
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。