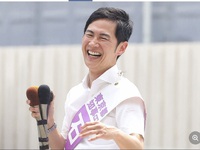2006年11月15日
教育のサービス産業化
ヒット商品応援団日記No116(毎週2回更新) 2006.11.15.
いじめ問題、履修不足問題など学校教育のあり方が問われている。幼児虐待も変わらず起こっており、子殺しもまた。私はこの春、「家族のゆくえ」でその崩壊のさまを既に書いてきたが、悪い予兆はこの1ヶ月ほどで大きく噴火してしまった。1990年代半ば、当時の文部省が指針として出した、「教師は教育というサービス業」という考え方に、当時の世相、社会を映し出していたと思う。文部科学省、教育委員会、学校長、現場教師、そして生徒と保護者、こうした教育に関わる役割において、平易にいうと民間企業と同じように、顧客は生徒と保護者であり、顧客が望むことをサービスするのが教師であるという考え方である。この考え方の延長線上には、顧客満足を数値化し、教師の評価につなげていく考え方となる。顧客満足は何かというと、志望する高校や大学への入学者数から始まり、しつけなど本来家庭で行うべきことまでサービス領域となる。「義務教育」は、本来家庭の事情などで行かせてあげられない貧しい時代の考え方から生まれたものである。今や、朝食抜きの子供が多く、学校で朝食サービスを行う小学校まで出てきている。つまり、社会の目やその価値がサービス産業的な見方に変化してきたからである。少し前に「マイブーム」というキーワードが流行ったが、マイティーチャー的価値を現場教師に求め始めたということだ。ここに矛盾点が凝縮されている。
さて、現場教師はと言えば福岡三輪中学校の教師のように「偽善者」「うそつき」呼ばわりし自殺への引き金を作っていた。勿論一部ではあるが、子供以下のどうしようもない教師がいる。学校長も右往左往するばかりで、とうとう自殺者まで出てきた。また、反対に学校長によるパワーハラスメント(いじめ)によって、自殺する現場教師がいかに多いか。教育を提供する側もまた崩壊している。
一方、先ほどの「顧客」である保護者及び子供はどうかと言えば、繰り返しになるが既に崩壊している。感情をコントロールできない子供たちを「キレル」と称して話題となったが、今や更に低年齢化し、保育所では「三歳児の崩壊」が始まっているという。人の話が聞けない、一人だけ走り回る、隣の子にかみつく・・・・・・箸を使えないばかりか、ボタンすらはめられない子供たちが急増していると聞く。母親はと言えば、平然と教師批判、サービス業としてのマネジメント能力不足を指摘する。
ここ半年ほど私が書いてきたテーマの多くは「回帰」についてであった。ふるさと回帰、自然(野生)への回帰、和回帰、こうした原点回帰は「都市化によって失ってしまったもの」をどう取り戻すかという視座であった。教育もまた原点回帰しなければならない。根源的には乳幼児期の母親の子育てから始めなければならないのだが、「今」という課題解決には遅すぎる。
企業の場合はどうかと言うと、一時期リストラなど行った結果、経済合理主義だけでは本当の顧客満足は得られないということが分かった。顧客の目は肥え、本物のサービスか否かを見極めるように成長している。例えば、アルバイトやパートといった経済合理だけの雇用形態では、本気・本物のサービスは難しいと正社員化を再び進め始めている。つまり、経済合理性だけでは経営できなくなってきているということである。意欲を持って仕事(顧客)に向かうには経済だけではなく、企業文化、企業風土、更には社会という見えざる価値の重要性に気づき始めたということである。もし、教育における原点回帰を志向するならば、学校、保護者、そして地域社会が交流しえる情報公開の場と時をつくり「今」を解決することだと思う。そして、一番重要なことは、江戸時代の大家さんのようなコミュニティリーダーの存在だ。(続く)
いじめ問題、履修不足問題など学校教育のあり方が問われている。幼児虐待も変わらず起こっており、子殺しもまた。私はこの春、「家族のゆくえ」でその崩壊のさまを既に書いてきたが、悪い予兆はこの1ヶ月ほどで大きく噴火してしまった。1990年代半ば、当時の文部省が指針として出した、「教師は教育というサービス業」という考え方に、当時の世相、社会を映し出していたと思う。文部科学省、教育委員会、学校長、現場教師、そして生徒と保護者、こうした教育に関わる役割において、平易にいうと民間企業と同じように、顧客は生徒と保護者であり、顧客が望むことをサービスするのが教師であるという考え方である。この考え方の延長線上には、顧客満足を数値化し、教師の評価につなげていく考え方となる。顧客満足は何かというと、志望する高校や大学への入学者数から始まり、しつけなど本来家庭で行うべきことまでサービス領域となる。「義務教育」は、本来家庭の事情などで行かせてあげられない貧しい時代の考え方から生まれたものである。今や、朝食抜きの子供が多く、学校で朝食サービスを行う小学校まで出てきている。つまり、社会の目やその価値がサービス産業的な見方に変化してきたからである。少し前に「マイブーム」というキーワードが流行ったが、マイティーチャー的価値を現場教師に求め始めたということだ。ここに矛盾点が凝縮されている。
さて、現場教師はと言えば福岡三輪中学校の教師のように「偽善者」「うそつき」呼ばわりし自殺への引き金を作っていた。勿論一部ではあるが、子供以下のどうしようもない教師がいる。学校長も右往左往するばかりで、とうとう自殺者まで出てきた。また、反対に学校長によるパワーハラスメント(いじめ)によって、自殺する現場教師がいかに多いか。教育を提供する側もまた崩壊している。
一方、先ほどの「顧客」である保護者及び子供はどうかと言えば、繰り返しになるが既に崩壊している。感情をコントロールできない子供たちを「キレル」と称して話題となったが、今や更に低年齢化し、保育所では「三歳児の崩壊」が始まっているという。人の話が聞けない、一人だけ走り回る、隣の子にかみつく・・・・・・箸を使えないばかりか、ボタンすらはめられない子供たちが急増していると聞く。母親はと言えば、平然と教師批判、サービス業としてのマネジメント能力不足を指摘する。
ここ半年ほど私が書いてきたテーマの多くは「回帰」についてであった。ふるさと回帰、自然(野生)への回帰、和回帰、こうした原点回帰は「都市化によって失ってしまったもの」をどう取り戻すかという視座であった。教育もまた原点回帰しなければならない。根源的には乳幼児期の母親の子育てから始めなければならないのだが、「今」という課題解決には遅すぎる。
企業の場合はどうかと言うと、一時期リストラなど行った結果、経済合理主義だけでは本当の顧客満足は得られないということが分かった。顧客の目は肥え、本物のサービスか否かを見極めるように成長している。例えば、アルバイトやパートといった経済合理だけの雇用形態では、本気・本物のサービスは難しいと正社員化を再び進め始めている。つまり、経済合理性だけでは経営できなくなってきているということである。意欲を持って仕事(顧客)に向かうには経済だけではなく、企業文化、企業風土、更には社会という見えざる価値の重要性に気づき始めたということである。もし、教育における原点回帰を志向するならば、学校、保護者、そして地域社会が交流しえる情報公開の場と時をつくり「今」を解決することだと思う。そして、一番重要なことは、江戸時代の大家さんのようなコミュニティリーダーの存在だ。(続く)
失われた30年nの意味
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
Posted by ヒット商品応援団 at 13:46│Comments(0)
│新市場創造