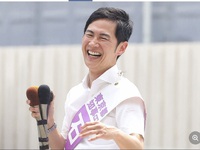2007年12月12日
心はどこへ向かうのか(1)
ヒット商品応援団日記No226(毎週2回更新) 2007.12.12.
島田洋七さんによるベストセラー「佐賀のがばいばあちゃん」に続いて、漫才コンビ麒麟の一人田村裕さんの「ホームレス中学生」が発売3ヶ月で100万部を超えるベストセラーとなった。「佐賀のがばいばあちゃん」が自費出版から始まり、長いこと売れずに島田洋七さんのTV出演を機に一挙に売れたのに対し、「ホームレス中学生」は、そのネーミングの強さもあり一挙にベストセラーとなった。本という商品を見ていくと、明らかに読者・生活者が求める一つの心性世界が見えてくる。消費が心理化していけばいくほど心性世界のあり方を読んでいくことが、消費構造解明への鍵となる。
「佐賀のがばいばあちゃん」が多くの人の心を動かしたのは、経済的には貧しくとも明るく生きる知恵、「Always三丁目の夕日」という心は過去へと向かう世界であった。「ホームレス中学生」はというと、まさに現代、差し迫った今を想起させる内容である。ネットカフェ難民どころか、とうとう中学生までホームレスになったのかという今を感じさせるものだ。島田洋七さんが団塊の世代であるのに対し、田村裕さんは28歳団塊ジュニアという時代の違いといっても良い。団塊世代の少年期は戦後ということからもほとんどの人は経済的には貧しかった。団塊世代の貧しさと豊かさ、団塊ジュニアの貧しさと豊かさ、この対比は時代そのものを映し出している。何も無かった昭和30年代から高度成長期を経て、一億総中流時代を経て、1990年代後半から格差が生まれ、そして文字通り貧富の時代が来たと表現してもよい。
「ホームレス中学生」はフィクションである「一杯のかけそば」を想起させる内容であるが、兄姉3人と亡き母との絆の実話である。時代のリアリティそのもので、リストラに遭った父から「もうこの家に住むことはできなくなりました。解散!」という一言から兄姉バラバラ、公園でのホームレス生活が始まる。当たり前にあった日常、当たり前のこととしてあった家族の絆はいとも簡単に崩れる時代である。作者の田村裕さんは、この「当たり前にあったこと」の大切さを亡き母との思い出を追想しながら、感謝の気持ちを書いていくという実話だ。明日は分からないという日常、不安を超えた恐怖に近い感情は家族・絆へと向かい、その心のありようが読者の心を打ったのだと思う。
引きこもりを始め、鬱病、摂食障害、子供ばかりかキレル大人、モンスターペアレント、モンスターペイシェント、個族となったストレス社会の病理のキーワードが続出する時代である。米国におけるメガ・チャーチのような心の相談窓口がない日本においてはコトは深刻である。風営法の改正により夜12時以降営業できない新宿のホストクラブは早朝営業を行っているが、OLを始め若い女性達で満杯となっている。小さなストレス解消グッズとしてあの「∞プチプチ」は150万個も売れ、中高生のケータイの待ち受け画面には、願いを叶えてくれるという元祖都市伝説の美輪明宏さんが使われる時代だ。個族となって漂流する心はどこへ向かっていくのだろうか、引き続き一つの仮説を書いてみたい。(続く)
島田洋七さんによるベストセラー「佐賀のがばいばあちゃん」に続いて、漫才コンビ麒麟の一人田村裕さんの「ホームレス中学生」が発売3ヶ月で100万部を超えるベストセラーとなった。「佐賀のがばいばあちゃん」が自費出版から始まり、長いこと売れずに島田洋七さんのTV出演を機に一挙に売れたのに対し、「ホームレス中学生」は、そのネーミングの強さもあり一挙にベストセラーとなった。本という商品を見ていくと、明らかに読者・生活者が求める一つの心性世界が見えてくる。消費が心理化していけばいくほど心性世界のあり方を読んでいくことが、消費構造解明への鍵となる。
「佐賀のがばいばあちゃん」が多くの人の心を動かしたのは、経済的には貧しくとも明るく生きる知恵、「Always三丁目の夕日」という心は過去へと向かう世界であった。「ホームレス中学生」はというと、まさに現代、差し迫った今を想起させる内容である。ネットカフェ難民どころか、とうとう中学生までホームレスになったのかという今を感じさせるものだ。島田洋七さんが団塊の世代であるのに対し、田村裕さんは28歳団塊ジュニアという時代の違いといっても良い。団塊世代の少年期は戦後ということからもほとんどの人は経済的には貧しかった。団塊世代の貧しさと豊かさ、団塊ジュニアの貧しさと豊かさ、この対比は時代そのものを映し出している。何も無かった昭和30年代から高度成長期を経て、一億総中流時代を経て、1990年代後半から格差が生まれ、そして文字通り貧富の時代が来たと表現してもよい。
「ホームレス中学生」はフィクションである「一杯のかけそば」を想起させる内容であるが、兄姉3人と亡き母との絆の実話である。時代のリアリティそのもので、リストラに遭った父から「もうこの家に住むことはできなくなりました。解散!」という一言から兄姉バラバラ、公園でのホームレス生活が始まる。当たり前にあった日常、当たり前のこととしてあった家族の絆はいとも簡単に崩れる時代である。作者の田村裕さんは、この「当たり前にあったこと」の大切さを亡き母との思い出を追想しながら、感謝の気持ちを書いていくという実話だ。明日は分からないという日常、不安を超えた恐怖に近い感情は家族・絆へと向かい、その心のありようが読者の心を打ったのだと思う。
引きこもりを始め、鬱病、摂食障害、子供ばかりかキレル大人、モンスターペアレント、モンスターペイシェント、個族となったストレス社会の病理のキーワードが続出する時代である。米国におけるメガ・チャーチのような心の相談窓口がない日本においてはコトは深刻である。風営法の改正により夜12時以降営業できない新宿のホストクラブは早朝営業を行っているが、OLを始め若い女性達で満杯となっている。小さなストレス解消グッズとしてあの「∞プチプチ」は150万個も売れ、中高生のケータイの待ち受け画面には、願いを叶えてくれるという元祖都市伝説の美輪明宏さんが使われる時代だ。個族となって漂流する心はどこへ向かっていくのだろうか、引き続き一つの仮説を書いてみたい。(続く)
失われた30年nの意味
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
Posted by ヒット商品応援団 at 13:43│Comments(0)
│新市場創造