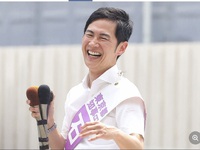2011年09月05日
流行歌(はやりうた)が聞こえない
ヒット商品応援団日記No518(毎週更新) 2011.9.5.
東日本大震災への義援金が、8月23日現在約250万件、2816億円を超えたと報じられた。昨年末から今年にかけて、児童養護施設に「伊達直人」を名乗る人物からランドセルを始めとしたプレゼントが送られ、そうした善意が連鎖しタイガーマスク運動になった。その時感じたのだが、日本人はなんとシャイで照れ屋が多いことかと。無縁社会が流行語になるようなバラバラ社会にあって、互いにタイガーマスクという記号を使って匿名のままつながりあう現象であったが、東日本大震災はそれとは異なる次元のものであった。シャイも照れもなく、3.11の光景は我が身の痛さとして突き刺さったからだ。その痛みとは目の前で、多くの命、家族や知人・友人の命を持ち去ったことへの痛みであり、更に家屋も、学校も、車も、町も、生活の全てを持ち去った自然そのものへの畏れが痛みとして突き刺さったということでもある。そして、その痛みが義援金や現地ボランティアへと向かわせた。
その痛みが今なお続いているからであろうか、歌が聞こえてこない。多くのミュージシャンやアーチストが被災地を訪れ、支援のコンサートなどを行っている。被災した人達へ、ひととき心安らいで欲しいという意味で貢献しているとは思うが、被災者と無名の応援者とを結ぶ、そんな応援歌は未だ生まれてはいない。
戦後生まれの団塊世代の私でも物心つく年齢になると、まだがれきの残る東京の荒廃した風景のなかに多くの流行歌(はやりうた)が聞こえていたことを覚えている。美空ひばりを筆頭に、春日八郎、三浦光一、三波春夫・・・・戦中を経験してきた私より上の世代にとってはこうした歌手による歌が応援歌になっていた。私の世代と言えば、その後の米国文化の象徴であるエルビスプレスリーやベンチャーズによるエレキブームとフォークソングであろう。
歌は時代を映し出すとは、表には出てこない生活者の心の底にたまった自分では解決出来ない澱んだ何かを歌によって何十分の一、ほんのひととき気持ちを楽にしてくれるものの一つであった。心の底に澱んでいたものは「自分」を超えた時代そのものが持つ、故郷への想いであったり、別れであったり、男と女の愛憎などをテーマとしたいわゆる歌謡曲の時代であった。また、そうした世界の裏表の関係として水前寺清子の「365歩のマーチ」のような希望や夢をテーマとした曲も広く流行った。
歌謡曲が日本人がもつ繊細な心情のひだを歌い上げたのに対し、フォークソングやロックはストレートなメッセージソングとして歌謡曲とともに流行った。福島原発事故後、反原発のロック(「SUMMER TIME BLUES」)として2年程前に癌で亡くなった忌野清志郎が注目されたが、時代をどう生きるか、ストレートなメッセージとして歌っていた。私の場合、忌野清志郎と言えば、代表曲「雨あがりの夜空に」が好きあるが。同時代を今なお生きているあの吉田拓郎は、ありのままの自分でいいじゃないか、時に疲れたら少し休もうじゃないか、というメッセージソング「ガンバラないけどいいでしょう」を最後に音楽活動を卒業した。
卒業と言えば、3年半程前になるだろうか、アンジェラ・アキが歌ったNHKの全国学校音楽コンクールの課題曲「拝啓 ありがとう 十五のあなたに伝えたい事があるのです」を思い出す。未来へと旅立つ中学生への応援歌「手紙」という曲であるが、まだそんな応援歌は出てきてはいない。
そもそも言葉の原初的発生は、最初はまさに音であった。うれしかったり、悲しかったりそうした感情は音、つまり表音としてあった。そうした音を人類は表意として、地域ごとに時代ごとに言語として制度化してきた。そうした意味で、音楽は原初としての言葉であった。この時代に言葉を与えてくれるミュージシャンは未だ出てきてはいない。まだまだ痛みは強く言葉にならないということだろうか。
亡くなった作詞家阿久悠は、晩年「昭和とともに終わったのは歌謡曲ではなく、実は、人間の心ではないかと気がついた」と語り、「心が無いとわかってしまうと、とても恐くて、新しいモラルや生き方を歌い上げることはできない」と歌づくりを断念した。しかし、3.11後の光景は痛みとともに、共助の光景をも見せてくれた。大津波は自助できるものを大きく超えたものであった。更に、頼りにすべき行政機関も津波で持ち去られ、残るは生き残った人々の共助だけとなった。多くの場合こうした災害後には略奪などが横行するのだが、日本の場合は互いに助け合う共助へと向かい、世界中から賞讃された。阿久悠は「心が無い」時代に歌うことはできないとしたが、実は心はあったのだ。
忌野清志郎が歌う「雨あがりの夜空に」の歌詞に次のようなフレーズがある。
・・・・・・・・・・・・
こんな夜におまえに乗れないなんて
こんな夜に発車でないなんて
こんなこといつまでも長くは続かない
・・・・・・・
Oh雨上がりの夜空にかがやく
Woo雲の切れ間に
散りばめたダイヤモンド
・・・・・・・・・・
そして、忌野清志郎は私たちに「どうしたんだHey Hey Baby」と投げかける。乱暴だが、とてつもなく優しい。そんな応援歌が待たれている。(続く)
東日本大震災への義援金が、8月23日現在約250万件、2816億円を超えたと報じられた。昨年末から今年にかけて、児童養護施設に「伊達直人」を名乗る人物からランドセルを始めとしたプレゼントが送られ、そうした善意が連鎖しタイガーマスク運動になった。その時感じたのだが、日本人はなんとシャイで照れ屋が多いことかと。無縁社会が流行語になるようなバラバラ社会にあって、互いにタイガーマスクという記号を使って匿名のままつながりあう現象であったが、東日本大震災はそれとは異なる次元のものであった。シャイも照れもなく、3.11の光景は我が身の痛さとして突き刺さったからだ。その痛みとは目の前で、多くの命、家族や知人・友人の命を持ち去ったことへの痛みであり、更に家屋も、学校も、車も、町も、生活の全てを持ち去った自然そのものへの畏れが痛みとして突き刺さったということでもある。そして、その痛みが義援金や現地ボランティアへと向かわせた。
その痛みが今なお続いているからであろうか、歌が聞こえてこない。多くのミュージシャンやアーチストが被災地を訪れ、支援のコンサートなどを行っている。被災した人達へ、ひととき心安らいで欲しいという意味で貢献しているとは思うが、被災者と無名の応援者とを結ぶ、そんな応援歌は未だ生まれてはいない。
戦後生まれの団塊世代の私でも物心つく年齢になると、まだがれきの残る東京の荒廃した風景のなかに多くの流行歌(はやりうた)が聞こえていたことを覚えている。美空ひばりを筆頭に、春日八郎、三浦光一、三波春夫・・・・戦中を経験してきた私より上の世代にとってはこうした歌手による歌が応援歌になっていた。私の世代と言えば、その後の米国文化の象徴であるエルビスプレスリーやベンチャーズによるエレキブームとフォークソングであろう。
歌は時代を映し出すとは、表には出てこない生活者の心の底にたまった自分では解決出来ない澱んだ何かを歌によって何十分の一、ほんのひととき気持ちを楽にしてくれるものの一つであった。心の底に澱んでいたものは「自分」を超えた時代そのものが持つ、故郷への想いであったり、別れであったり、男と女の愛憎などをテーマとしたいわゆる歌謡曲の時代であった。また、そうした世界の裏表の関係として水前寺清子の「365歩のマーチ」のような希望や夢をテーマとした曲も広く流行った。
歌謡曲が日本人がもつ繊細な心情のひだを歌い上げたのに対し、フォークソングやロックはストレートなメッセージソングとして歌謡曲とともに流行った。福島原発事故後、反原発のロック(「SUMMER TIME BLUES」)として2年程前に癌で亡くなった忌野清志郎が注目されたが、時代をどう生きるか、ストレートなメッセージとして歌っていた。私の場合、忌野清志郎と言えば、代表曲「雨あがりの夜空に」が好きあるが。同時代を今なお生きているあの吉田拓郎は、ありのままの自分でいいじゃないか、時に疲れたら少し休もうじゃないか、というメッセージソング「ガンバラないけどいいでしょう」を最後に音楽活動を卒業した。
卒業と言えば、3年半程前になるだろうか、アンジェラ・アキが歌ったNHKの全国学校音楽コンクールの課題曲「拝啓 ありがとう 十五のあなたに伝えたい事があるのです」を思い出す。未来へと旅立つ中学生への応援歌「手紙」という曲であるが、まだそんな応援歌は出てきてはいない。
そもそも言葉の原初的発生は、最初はまさに音であった。うれしかったり、悲しかったりそうした感情は音、つまり表音としてあった。そうした音を人類は表意として、地域ごとに時代ごとに言語として制度化してきた。そうした意味で、音楽は原初としての言葉であった。この時代に言葉を与えてくれるミュージシャンは未だ出てきてはいない。まだまだ痛みは強く言葉にならないということだろうか。
亡くなった作詞家阿久悠は、晩年「昭和とともに終わったのは歌謡曲ではなく、実は、人間の心ではないかと気がついた」と語り、「心が無いとわかってしまうと、とても恐くて、新しいモラルや生き方を歌い上げることはできない」と歌づくりを断念した。しかし、3.11後の光景は痛みとともに、共助の光景をも見せてくれた。大津波は自助できるものを大きく超えたものであった。更に、頼りにすべき行政機関も津波で持ち去られ、残るは生き残った人々の共助だけとなった。多くの場合こうした災害後には略奪などが横行するのだが、日本の場合は互いに助け合う共助へと向かい、世界中から賞讃された。阿久悠は「心が無い」時代に歌うことはできないとしたが、実は心はあったのだ。
忌野清志郎が歌う「雨あがりの夜空に」の歌詞に次のようなフレーズがある。
・・・・・・・・・・・・
こんな夜におまえに乗れないなんて
こんな夜に発車でないなんて
こんなこといつまでも長くは続かない
・・・・・・・
Oh雨上がりの夜空にかがやく
Woo雲の切れ間に
散りばめたダイヤモンド
・・・・・・・・・・
そして、忌野清志郎は私たちに「どうしたんだHey Hey Baby」と投げかける。乱暴だが、とてつもなく優しい。そんな応援歌が待たれている。(続く)
失われた30年nの意味
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
Posted by ヒット商品応援団 at 09:40│Comments(0)
│新市場創造
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。