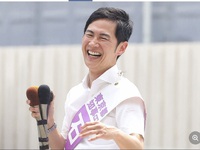2007年08月08日
新たな過剰対策
ヒット商品応援団日記No191(毎週2回更新) 2007.8.8.
1990年代半ば以降、多くの過剰を合併、業務提携、最悪では倒産というかたちで再編されてきた。その先鞭は銀行や証券といった金融業界(拓銀、長銀や山一証券)であったが、更に自動車、建設あらゆる業界へと進んで来た。そして、今なお、大学を始めとした教育ビジネスの再編、白物家電を中心とした家電メーカーの再編、流通においては今回の三越と伊勢丹の合併による再編、生活の隅々まで再編が行われてきた。
こうした再編を促して来たのがグローバリズム、世界を単一市場として見ていくビジネスであるが、その象徴例として米国で面白いプロモーションが始まっている。世界の工場中国製品に対するもので、相次ぐドッグフーズを始めとした問題に対し、「CHINA FREE 」中国産の原材料は使っていませんという新しい差別化プロモーションが盛んである。日本でもこの時期飛ぶように売れる土用のうなぎも中国産が70%を占めていることから売上は半減以下と言われている。日々の生活ですら視野を世界に求めないと安心していられない時代だ。
このブログでも東京ミッドタウンや東京駅新丸ビル、あるいは都心百貨店のコンセプトの傾向を書いて来たが、東京はTOKYOとなり、世界の新しいブランドや飲食が続々と集積している。また同時に日本国内にある埋もれた名店、銘品が発掘されMDされてきている。
先日、地方活性化を担っているいくつかの各県のパイロットショップを見て回ったが、東国原=宮崎ブームにのって宮崎県以外の県産品にも人が集まっている。特に東京がそうであると思うが、多種多彩なモノ、特に食品、飲食の集積スピードが速く、何か次なる「過剰」時代に入った感がしてならない。特に、食は生活者にとって価格的にも取り入れやすいということから、安易とは言わないが県産品のプロモーションが盛んである。「今、地方が面白い」とこのブログで書いた私であるが、ビジネス継続を視野に入れないと、次なる再編の時代を迎えることとなる。単なる「物珍しさ」から、生活の中に組み込まれていくようなものということだ。
この10年位、こうした傾向に対し、1つの業態・ブランドで100億という規模ビジネスモデルから、10の業態・ブランドで100億というビジネスモデルへと変えて来た。しかし、こうした過剰さに対し、更にこの単位を小さくしていくことが求められていると思う。
つまり、日本国内という市場に限定した話であるが、新たな過剰に対し、より小さな単位で成立するビジネスモデルが求められてくる。今までのビジネス、店舗で言えば10坪を5坪に、運営スタッフを4人から2人へ、勿論商品アイテム数も半分に、売上が半分であっても投資を半分以下にすれば資本利益率、キャッシュフローは良くなる。この回転の速度と精度が現場経営のポイントとなる。新たな過剰に対し、更なるスモールビジネス化が必要となってくる。(続く)
1990年代半ば以降、多くの過剰を合併、業務提携、最悪では倒産というかたちで再編されてきた。その先鞭は銀行や証券といった金融業界(拓銀、長銀や山一証券)であったが、更に自動車、建設あらゆる業界へと進んで来た。そして、今なお、大学を始めとした教育ビジネスの再編、白物家電を中心とした家電メーカーの再編、流通においては今回の三越と伊勢丹の合併による再編、生活の隅々まで再編が行われてきた。
こうした再編を促して来たのがグローバリズム、世界を単一市場として見ていくビジネスであるが、その象徴例として米国で面白いプロモーションが始まっている。世界の工場中国製品に対するもので、相次ぐドッグフーズを始めとした問題に対し、「CHINA FREE 」中国産の原材料は使っていませんという新しい差別化プロモーションが盛んである。日本でもこの時期飛ぶように売れる土用のうなぎも中国産が70%を占めていることから売上は半減以下と言われている。日々の生活ですら視野を世界に求めないと安心していられない時代だ。
このブログでも東京ミッドタウンや東京駅新丸ビル、あるいは都心百貨店のコンセプトの傾向を書いて来たが、東京はTOKYOとなり、世界の新しいブランドや飲食が続々と集積している。また同時に日本国内にある埋もれた名店、銘品が発掘されMDされてきている。
先日、地方活性化を担っているいくつかの各県のパイロットショップを見て回ったが、東国原=宮崎ブームにのって宮崎県以外の県産品にも人が集まっている。特に東京がそうであると思うが、多種多彩なモノ、特に食品、飲食の集積スピードが速く、何か次なる「過剰」時代に入った感がしてならない。特に、食は生活者にとって価格的にも取り入れやすいということから、安易とは言わないが県産品のプロモーションが盛んである。「今、地方が面白い」とこのブログで書いた私であるが、ビジネス継続を視野に入れないと、次なる再編の時代を迎えることとなる。単なる「物珍しさ」から、生活の中に組み込まれていくようなものということだ。
この10年位、こうした傾向に対し、1つの業態・ブランドで100億という規模ビジネスモデルから、10の業態・ブランドで100億というビジネスモデルへと変えて来た。しかし、こうした過剰さに対し、更にこの単位を小さくしていくことが求められていると思う。
つまり、日本国内という市場に限定した話であるが、新たな過剰に対し、より小さな単位で成立するビジネスモデルが求められてくる。今までのビジネス、店舗で言えば10坪を5坪に、運営スタッフを4人から2人へ、勿論商品アイテム数も半分に、売上が半分であっても投資を半分以下にすれば資本利益率、キャッシュフローは良くなる。この回転の速度と精度が現場経営のポイントとなる。新たな過剰に対し、更なるスモールビジネス化が必要となってくる。(続く)
失われた30年nの意味
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
Posted by ヒット商品応援団 at 11:30│Comments(0)
│新市場創造