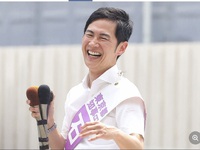2009年01月21日
訳あり実感劇場
ヒット商品応援団日記No334(毎週2回更新) 2009.1.21.
麻生首相の読み間違いから漢字教養本「読めそうで読めない間違いやすい漢字」が売れているという。人のふり見て我がふり直せではないが、私のブログでも漢字の使い方が間違っていると指摘のコメントが寄せられたことがある。確かに、こうした漢字教養本が売れていくのはこうした背景があるのだなと思った。が、同時に読み間違いは普段読んでいない、使っていないからであろうとも思った。つまり、問題は読み間違いではなく、実感のないまましゃべったり、使ったりしていることにあると。
ビジネス書、マーケティング書が全く売れないのも、知識ではなく、意味ある実務、実感が伴わないためである。先日沖縄で小さな勉強会を行ってきたが、塾生に焼き鳥の移動販売をする参加者がいた。見れば分かるが、圧縮され小さくなった「オープンキッチン」で「移動する」「店舗」と思えば分かりやすい。オープンキッチンの良さを2倍3倍にする工夫、店舗の魅力を高めるためのアイディア、更に移動によって生まれる新しい市場開拓の可能性といった具合に議論してきた。このブログでも繰り返し書いてきたが、小さな単位、小さく見ていくことによって使えるアイディアが生まれてくる。
3年ほど前、ベストセラーとなった「えんぴつで奥の細道」についてふれたことがあった。PCまかせでスピードを競うデジタル世界ではほとんど書くという行為はない時代だ。ましてや、鉛筆など持つことがない日常である。そうした中、書を担当された大迫閑歩さんは「紀行文を読む行為が闊歩することだとしたら、書くとは路傍の花を見ながら道草を食うようなもの」と話されていた。道草とは、ある意味自らの自由な感性を取り戻すことでもある。
便利さを追求していくことは決して悪いことではないが、技術の進歩による高機能商品に囲まれた快適な生活によって失ったものもある。その最大のものが五感の喪失であろう。五感は外の世界を感知する、視覚、聴覚、触覚、味覚、臭覚、の5つを一般的には指し示す言葉である。極論ではあるが現代は「無感社会」になりつつあるように思えて仕方が無い。無感こそが快適であるとして、人が本来持っている「野生」を無くしているように思える。
この2年ほど見えない世界での情報偽装、更には金融工学というこれまた見えない世界によって引き起こされた不況下で、今生活者は籠った巣のなかで便利さを横に見ながら、今一度生活の原点に立ち戻りつつある。生活とは、読んで字の如く、生き生きと暮らすことに他ならない。つまり、五感そのものとしての暮らしである。既にブームを終え定着しつつある家庭菜園も、単なる自己防衛としてでなく、自然を自らの手で育て収穫する五感生活の一つであろう。
ところで、生活を実感化させていく顧客に応えるには、提供する側も五感を引き出すようにMDあるいはマーケティングしなければならない。焼きたて、煮たばかり、蒸したて、今作ったばかりという視覚に映し出される鮮度。臭い立ち、あたかも味覚が感じとれるような商品。ファッションであれば、時代の雰囲気を表した、手に馴染む、肌に馴染む、身体にしっくりとしたスタイリング、ということになる。365日欲しい物が手に入る時代で、旬という言葉が死語になりつつある時代だ。そうであればこそ、商品達の店頭舞台は、顧客にとっての実感劇場となる。時を感じさせる、何故そうなのか安い訳・高い訳といったテーマを感じさせる、その土地・エリアならではを感じさせる、そしてその作り手ならではを感じさせる、そんな訳あり実感劇場である。(続く)
麻生首相の読み間違いから漢字教養本「読めそうで読めない間違いやすい漢字」が売れているという。人のふり見て我がふり直せではないが、私のブログでも漢字の使い方が間違っていると指摘のコメントが寄せられたことがある。確かに、こうした漢字教養本が売れていくのはこうした背景があるのだなと思った。が、同時に読み間違いは普段読んでいない、使っていないからであろうとも思った。つまり、問題は読み間違いではなく、実感のないまましゃべったり、使ったりしていることにあると。
ビジネス書、マーケティング書が全く売れないのも、知識ではなく、意味ある実務、実感が伴わないためである。先日沖縄で小さな勉強会を行ってきたが、塾生に焼き鳥の移動販売をする参加者がいた。見れば分かるが、圧縮され小さくなった「オープンキッチン」で「移動する」「店舗」と思えば分かりやすい。オープンキッチンの良さを2倍3倍にする工夫、店舗の魅力を高めるためのアイディア、更に移動によって生まれる新しい市場開拓の可能性といった具合に議論してきた。このブログでも繰り返し書いてきたが、小さな単位、小さく見ていくことによって使えるアイディアが生まれてくる。
3年ほど前、ベストセラーとなった「えんぴつで奥の細道」についてふれたことがあった。PCまかせでスピードを競うデジタル世界ではほとんど書くという行為はない時代だ。ましてや、鉛筆など持つことがない日常である。そうした中、書を担当された大迫閑歩さんは「紀行文を読む行為が闊歩することだとしたら、書くとは路傍の花を見ながら道草を食うようなもの」と話されていた。道草とは、ある意味自らの自由な感性を取り戻すことでもある。
便利さを追求していくことは決して悪いことではないが、技術の進歩による高機能商品に囲まれた快適な生活によって失ったものもある。その最大のものが五感の喪失であろう。五感は外の世界を感知する、視覚、聴覚、触覚、味覚、臭覚、の5つを一般的には指し示す言葉である。極論ではあるが現代は「無感社会」になりつつあるように思えて仕方が無い。無感こそが快適であるとして、人が本来持っている「野生」を無くしているように思える。
この2年ほど見えない世界での情報偽装、更には金融工学というこれまた見えない世界によって引き起こされた不況下で、今生活者は籠った巣のなかで便利さを横に見ながら、今一度生活の原点に立ち戻りつつある。生活とは、読んで字の如く、生き生きと暮らすことに他ならない。つまり、五感そのものとしての暮らしである。既にブームを終え定着しつつある家庭菜園も、単なる自己防衛としてでなく、自然を自らの手で育て収穫する五感生活の一つであろう。
ところで、生活を実感化させていく顧客に応えるには、提供する側も五感を引き出すようにMDあるいはマーケティングしなければならない。焼きたて、煮たばかり、蒸したて、今作ったばかりという視覚に映し出される鮮度。臭い立ち、あたかも味覚が感じとれるような商品。ファッションであれば、時代の雰囲気を表した、手に馴染む、肌に馴染む、身体にしっくりとしたスタイリング、ということになる。365日欲しい物が手に入る時代で、旬という言葉が死語になりつつある時代だ。そうであればこそ、商品達の店頭舞台は、顧客にとっての実感劇場となる。時を感じさせる、何故そうなのか安い訳・高い訳といったテーマを感じさせる、その土地・エリアならではを感じさせる、そしてその作り手ならではを感じさせる、そんな訳あり実感劇場である。(続く)
失われた30年nの意味
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
Posted by ヒット商品応援団 at 13:18│Comments(0)
│新市場創造
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。