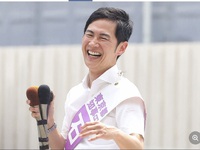2021年03月12日
今なお、切に生きる
ヒット商品応援団日記No782(毎週更新) 2021.3.12.

3.11東日本大震災が10年を迎えた。ここ1週間ほどNHKを始め民放各局は10年という節目として何が変わり何が変わらないのか、復旧・復興はどこまで進んだのかをレポートしていたが、取材を受ける被災者の多くは「節目」などないと答えていた。そこには今なお必死な想いが横たわっていることに気づく。
「切に生きる」という言葉は、2011年文芸春秋の5月号の特集「日本人の再出発」に瀬戸内寂聴さんが病床にあって手記を寄せた文の中で使われたキーワードである。「今こそ、切に生きる」と題し、好きな道元禅師の言葉を引用して、「切に生きる」ことの勧めを説いていた。「切に生きる」とは、ひたすら生きるということである。いまこの一瞬一瞬をひたむきに生きるということである。それが被災し亡くなられた家族や多くの人達に、生きている私たちに出来ることだと。
寂聴さんの言葉を借りれば、苦しい死の床にあるこの場所も自分を高めていく道場。道元はこの言葉を唱えながら亡くなったという。「はかない人生を送ってはならない。切に生きよ」、道元が死の床で弟子たちに残した最期のメッセージである。
震災2ヶ月後、「人間が人間であるための故郷」というタイトルでブログを書いた。2011年当時東北三県の人口は約570万人、10年後の現在532万人(-6.6%)38万人の減少となっている。特に津波の被害が大きかった宮城県女川町(-43.3%)のように「復興」とは程遠い状態である。
また、地震・津波と共に大きな被災となったのが原発事故による福島県である。原発の北側にある双葉町は今なお解除されていないが、解除地域に住民登録がある人のうち実際に住む人 31.6%(1万4375人)。今なお避難している、もしくは故郷を帰ることを諦めた人がいかに多いかがわかる。ちなみに、楢葉町59.7%(4038人)、南相馬市56%(4305人)、富岡町17.7%(1576人)、浪江町11.4%(1579人)。
当時「人間が人間であるための故郷」、その故郷について次のように書いた。
『福島原発事故の避難地域住民の人も、岩手や宮城の津波によって家も家族も根こそぎ奪われた人も、必ず口にする言葉に故郷がある。故郷に戻りたい、故郷を復興させたいという思いで口にするのであるが、故郷という言葉を聴くと、国民的な人気マンガ・アニメであるちびまる子ちゃんの世界が想起される。周知のさくらももこが生まれ育った静岡県清水市を舞台にした1970年代の日常を描いたものであるが、ここには日本の原風景である生活、家族、友人が生き生きと、時に切ない思いで登場している。故郷は日常そのもののなかにあるということだ。そして、その日常とは住まいがあり、仕事や学びの場所があり、そして移動する鉄道がある。がれきの山となった被災地で写真を始めとした思い出を探す光景が報じられるが、それら全て日常の思い出探しである。
誰もが思うことであるが、転勤で国内外を問わず転々ととする人も多いが、やはり帰る場所、故郷があっての話しである。今回の東日本大震災は、一種の帰巣本能のように、がれきの向こう側に突如として故郷が思い出され、帰りたいと、それが故郷であった。しかし、巨大津波で根こそぎ故郷を奪われてしまった海岸線の人も、放射能汚染によって立ち入ることすら制限されている福島原発周辺の人にとっても、故郷を失ったデラシネの人となってしまう恐れがある。』
震災による窮状に苦しむ住民への思いを胸に、いち早く立ち上がった多くの市町村長の行動があった。 米タイム誌は21日発表した「世界で最も影響力のある100人」に、福島原発事故での政府対応をYouTubeで厳しく批判した福島県南相馬市の桜井勝延市長。あるいは、郡山市の原市長は「国と東京電力は、郡山市民、福島県民の命を第一とし、『廃炉』を前提としたアメリカ合衆国からの支援を断ったことは言語道断であります。私は、郡山市民を代表して、さらには、福島県民として、今回の原発事故には、『廃炉』を前提として対応することとし、スリーマイル島の原発事故を経験しているアメリカ合衆国からの支援を早急に受け入れ、一刻も早く原発事故の沈静化を図るよう国及び東京電力に対し、強く要望する」と記者発表した。
行政にとって地域住民が全てである。理屈ではなく、住民への思い、哲学があって初めて行政サービスが行えるということだ。どこの首長であったか忘れてしまったが、財布も持たずに着の身着のままで避難所暮らしをすることになった被災者に対し、何よりも必要となる現金、確か一時金として10万円を支給した地方自治体があった。被災地の再生にバイオマスによるエコタウン構想・・・・・・そんなことではなく、プライベートな生活が確保できる仮設住宅こそが必要であった。子ども達の健康を考え、校庭の表土を自らの判断で除去した自治体もあった。あるいは、岩手の三陸海岸沿いの孤立した集落では、行政は壊滅し、まさに住民自ら自治を行っているコミュニティがいかに多かったか。求められる日常をいかに取り戻すか、いかに新しくつくっていくか、これが生活者への、被災者への哲学である。
そして、行政と共に、この故郷を取り戻す活動は震災後すぐにスタートした。震災後49日間で東北新幹線は復旧し、新青森から鹿児島までつながることとなる。これを機会に東北を元気づけるために、観光客を誘致することをマスメディアは盛んに報じるが、それはそれとして必要とは思ったが、地元の足である在来線である東北本線が少し前に復旧したことの方がうれしい話である。あるいは東北自動車道開通もそうであったが、コンビニのローソンもイオンのSCも被災地で復旧オープンさせたことの方が大きな意味を持つ。それは被災地にとって、日常に一歩、故郷に一歩近づくことであるからだ。故郷とは人がいて笑い声が聞こえる賑わいであることがわかる。故郷は単なる風景としてのそれではなく、人がいる風景のことである。
震災直後はまさに自助共助公助であった。しかし、故郷は帰ることことができる場所であるが、福島を始めその故郷を失い、もしくは断念した人がいかに多いか。一方今なお故郷にとどまり「切に生きる」人たちも多い。その中で偶然TVのニュースで知った一人が福島在住の臨床医坪倉医師である。東日本大震災、中でも放射能汚染にみまわれた福島県の医療再生に今なお貢献している医師の一人である。その中心となっているのが坪倉正治氏であるが、地域医療の再生プロジェクトを立ち上げ全国から同じ志を持った医師と共に再生を目指している現場の医師である。臨床医であると同時に多くの放射能汚染に関する論文を世界に向けて発表するだけでなく、福島の地元のこともたちに「放射能とは何か」をやさしく話聞かせてくれる先生でもある。
新型コロナウイルスと放射能も異なるものだが、同じ「見えない世界」である。坪倉正治氏が小学生にもわかるように語りかけることが今最も必要となっている。感染症の専門家による「講義」などではないということだ。小学生に語りかける「坪倉正治氏の放射線教室」は今もなお作家村上龍のJMMで配信されている。東京のマスメディアは決して取り上げることのない坪倉医師をニュース画面で見かけたのは、あの元オリンピック組織委員会会長森氏の女性蔑視発言の直後であった。復興五輪ということから聖火リレーの参加表明して来たが、復興とはまるで異なる運営となっている東京オリンピックには関わらない、そんなニュースであった。坪倉医師は今もなお放射能汚染と闘っており、明日も闘っていくであろう人たちの一人である。「切に生きる」人たちにとって、「復興」という冠のないオリンピックは意味のないイベントであるということだ。
ところで、その原発事故の「今」について、改めて気づかされたのがNHKスペシャルの2つの番組、「徹底検証 原発マネー」及び「廃炉への道」であった。今なお、というより廃炉への道筋が不透明の中の原発事故関連の「お金」の使われ方である。
新聞などを通じての報道に触れることはあったが、時々の断片的な情報であり、この廃炉・除染という困難さの全体を感じ取ることはなかなかできなかった。史上最悪規模の事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所。10年経ってやっと溶け落ちた核燃料を取り出し、処分する「廃炉」が始まろうとしている。40年ともいわれる長い時間をかけて、3つの原子炉を「廃炉」する人類史上例を見ない試みはどのような経過をたどるのか。放射能との長きにわたる闘いを、長期に渡り多角的に記録していくものだが始まりは水素爆発をきっかけにメルトダウンが起き、膨大な量の放射能がまきちらかされる。多くの原子力研究者が既にメルトダウンが起きていると指摘したにも関わらず、「メルトダウンではない」と言い張った当時の菅直人政権の官房長官の姿が思い出される。
コロナ禍の1年を経験し、3.11当時の「社会」を振り返ると多くを失ったが今なお切に生きる人たちがいることを通説に感じる。そして、「現在」との比較をどうしてもしてしまう。一言で言えば、復旧・復興に向け社会が災害に向かうという緊張感のある「一体感」があった。しかし、現在はどうかと言えば、緊急事態制限発出や延長に関し、政府と東京都との間での駆け引きを見るにつけ、東日本大震災当時の住民本位である行政とのあまりに大きな違いに唖然とする。以降、防災については多くの面で学びそして進化して来た。しかし、「政治」は逆に退化し続けている。
亡くなった作詞家阿久悠さんは、晩年「昭和とともに終わったのは歌謡曲ではなく、実は、人間の心ではないかと気がついた」と語り、「心が無いとわかってしまうと、とても恐くて、新しいモラルや生き方を歌い上げることはできない」と歌づくりを断念した。しかし、3.11後の光景は痛みとともに、「絆」というキーワードに表される共助の光景をも見せてくれた。大津波は自助できるものを大きく超えたものであった。更に、頼りにすべき行政機関も津波で持ち去られ、残るは生き残った人々の共助だけとなった。多くの場合こうした災害後には略奪などが横行するのだが、日本の場合は互いに助け合う共助へと向かい、世界中から賞讃された。阿久悠さんは「心が無い」時代に歌うことはできないとしたが、実は東北には心はあったのだ。今一度10年前の東日本大震災の原点に戻らなければならない。
忌野清志郎が歌う「雨あがりの夜空に」の歌詞に次のようなフレーズがある。
・・・・・・・・・・・・
こんな夜におまえに乗れないなんて
こんな夜に発車でないなんて
こんなこといつまでも長くは続かない
・・・・・・・
Oh雨上がりの夜空にかがやく
Woo雲の切れ間に
散りばめたダイヤモンド
・・・・・・・・・・
そして、忌野清志郎は私たちに「どうしたんだHey Hey Baby」と投げかける。乱暴だが、とてつもなく優しい。「切に生きる」人たちへ、そんな応援歌が待たれている。今なお、戦いは続いているということだ。(続く)
追記 テーマから言うと大津波などの画像の方がわかりやすいが、やはり胸が苦しくなり、好きな忌野清志郎の応援歌の写真を使うこととした。

3.11東日本大震災が10年を迎えた。ここ1週間ほどNHKを始め民放各局は10年という節目として何が変わり何が変わらないのか、復旧・復興はどこまで進んだのかをレポートしていたが、取材を受ける被災者の多くは「節目」などないと答えていた。そこには今なお必死な想いが横たわっていることに気づく。
「切に生きる」という言葉は、2011年文芸春秋の5月号の特集「日本人の再出発」に瀬戸内寂聴さんが病床にあって手記を寄せた文の中で使われたキーワードである。「今こそ、切に生きる」と題し、好きな道元禅師の言葉を引用して、「切に生きる」ことの勧めを説いていた。「切に生きる」とは、ひたすら生きるということである。いまこの一瞬一瞬をひたむきに生きるということである。それが被災し亡くなられた家族や多くの人達に、生きている私たちに出来ることだと。
寂聴さんの言葉を借りれば、苦しい死の床にあるこの場所も自分を高めていく道場。道元はこの言葉を唱えながら亡くなったという。「はかない人生を送ってはならない。切に生きよ」、道元が死の床で弟子たちに残した最期のメッセージである。
震災2ヶ月後、「人間が人間であるための故郷」というタイトルでブログを書いた。2011年当時東北三県の人口は約570万人、10年後の現在532万人(-6.6%)38万人の減少となっている。特に津波の被害が大きかった宮城県女川町(-43.3%)のように「復興」とは程遠い状態である。
また、地震・津波と共に大きな被災となったのが原発事故による福島県である。原発の北側にある双葉町は今なお解除されていないが、解除地域に住民登録がある人のうち実際に住む人 31.6%(1万4375人)。今なお避難している、もしくは故郷を帰ることを諦めた人がいかに多いかがわかる。ちなみに、楢葉町59.7%(4038人)、南相馬市56%(4305人)、富岡町17.7%(1576人)、浪江町11.4%(1579人)。
当時「人間が人間であるための故郷」、その故郷について次のように書いた。
『福島原発事故の避難地域住民の人も、岩手や宮城の津波によって家も家族も根こそぎ奪われた人も、必ず口にする言葉に故郷がある。故郷に戻りたい、故郷を復興させたいという思いで口にするのであるが、故郷という言葉を聴くと、国民的な人気マンガ・アニメであるちびまる子ちゃんの世界が想起される。周知のさくらももこが生まれ育った静岡県清水市を舞台にした1970年代の日常を描いたものであるが、ここには日本の原風景である生活、家族、友人が生き生きと、時に切ない思いで登場している。故郷は日常そのもののなかにあるということだ。そして、その日常とは住まいがあり、仕事や学びの場所があり、そして移動する鉄道がある。がれきの山となった被災地で写真を始めとした思い出を探す光景が報じられるが、それら全て日常の思い出探しである。
誰もが思うことであるが、転勤で国内外を問わず転々ととする人も多いが、やはり帰る場所、故郷があっての話しである。今回の東日本大震災は、一種の帰巣本能のように、がれきの向こう側に突如として故郷が思い出され、帰りたいと、それが故郷であった。しかし、巨大津波で根こそぎ故郷を奪われてしまった海岸線の人も、放射能汚染によって立ち入ることすら制限されている福島原発周辺の人にとっても、故郷を失ったデラシネの人となってしまう恐れがある。』
震災による窮状に苦しむ住民への思いを胸に、いち早く立ち上がった多くの市町村長の行動があった。 米タイム誌は21日発表した「世界で最も影響力のある100人」に、福島原発事故での政府対応をYouTubeで厳しく批判した福島県南相馬市の桜井勝延市長。あるいは、郡山市の原市長は「国と東京電力は、郡山市民、福島県民の命を第一とし、『廃炉』を前提としたアメリカ合衆国からの支援を断ったことは言語道断であります。私は、郡山市民を代表して、さらには、福島県民として、今回の原発事故には、『廃炉』を前提として対応することとし、スリーマイル島の原発事故を経験しているアメリカ合衆国からの支援を早急に受け入れ、一刻も早く原発事故の沈静化を図るよう国及び東京電力に対し、強く要望する」と記者発表した。
行政にとって地域住民が全てである。理屈ではなく、住民への思い、哲学があって初めて行政サービスが行えるということだ。どこの首長であったか忘れてしまったが、財布も持たずに着の身着のままで避難所暮らしをすることになった被災者に対し、何よりも必要となる現金、確か一時金として10万円を支給した地方自治体があった。被災地の再生にバイオマスによるエコタウン構想・・・・・・そんなことではなく、プライベートな生活が確保できる仮設住宅こそが必要であった。子ども達の健康を考え、校庭の表土を自らの判断で除去した自治体もあった。あるいは、岩手の三陸海岸沿いの孤立した集落では、行政は壊滅し、まさに住民自ら自治を行っているコミュニティがいかに多かったか。求められる日常をいかに取り戻すか、いかに新しくつくっていくか、これが生活者への、被災者への哲学である。
そして、行政と共に、この故郷を取り戻す活動は震災後すぐにスタートした。震災後49日間で東北新幹線は復旧し、新青森から鹿児島までつながることとなる。これを機会に東北を元気づけるために、観光客を誘致することをマスメディアは盛んに報じるが、それはそれとして必要とは思ったが、地元の足である在来線である東北本線が少し前に復旧したことの方がうれしい話である。あるいは東北自動車道開通もそうであったが、コンビニのローソンもイオンのSCも被災地で復旧オープンさせたことの方が大きな意味を持つ。それは被災地にとって、日常に一歩、故郷に一歩近づくことであるからだ。故郷とは人がいて笑い声が聞こえる賑わいであることがわかる。故郷は単なる風景としてのそれではなく、人がいる風景のことである。
震災直後はまさに自助共助公助であった。しかし、故郷は帰ることことができる場所であるが、福島を始めその故郷を失い、もしくは断念した人がいかに多いか。一方今なお故郷にとどまり「切に生きる」人たちも多い。その中で偶然TVのニュースで知った一人が福島在住の臨床医坪倉医師である。東日本大震災、中でも放射能汚染にみまわれた福島県の医療再生に今なお貢献している医師の一人である。その中心となっているのが坪倉正治氏であるが、地域医療の再生プロジェクトを立ち上げ全国から同じ志を持った医師と共に再生を目指している現場の医師である。臨床医であると同時に多くの放射能汚染に関する論文を世界に向けて発表するだけでなく、福島の地元のこともたちに「放射能とは何か」をやさしく話聞かせてくれる先生でもある。
新型コロナウイルスと放射能も異なるものだが、同じ「見えない世界」である。坪倉正治氏が小学生にもわかるように語りかけることが今最も必要となっている。感染症の専門家による「講義」などではないということだ。小学生に語りかける「坪倉正治氏の放射線教室」は今もなお作家村上龍のJMMで配信されている。東京のマスメディアは決して取り上げることのない坪倉医師をニュース画面で見かけたのは、あの元オリンピック組織委員会会長森氏の女性蔑視発言の直後であった。復興五輪ということから聖火リレーの参加表明して来たが、復興とはまるで異なる運営となっている東京オリンピックには関わらない、そんなニュースであった。坪倉医師は今もなお放射能汚染と闘っており、明日も闘っていくであろう人たちの一人である。「切に生きる」人たちにとって、「復興」という冠のないオリンピックは意味のないイベントであるということだ。
ところで、その原発事故の「今」について、改めて気づかされたのがNHKスペシャルの2つの番組、「徹底検証 原発マネー」及び「廃炉への道」であった。今なお、というより廃炉への道筋が不透明の中の原発事故関連の「お金」の使われ方である。
新聞などを通じての報道に触れることはあったが、時々の断片的な情報であり、この廃炉・除染という困難さの全体を感じ取ることはなかなかできなかった。史上最悪規模の事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所。10年経ってやっと溶け落ちた核燃料を取り出し、処分する「廃炉」が始まろうとしている。40年ともいわれる長い時間をかけて、3つの原子炉を「廃炉」する人類史上例を見ない試みはどのような経過をたどるのか。放射能との長きにわたる闘いを、長期に渡り多角的に記録していくものだが始まりは水素爆発をきっかけにメルトダウンが起き、膨大な量の放射能がまきちらかされる。多くの原子力研究者が既にメルトダウンが起きていると指摘したにも関わらず、「メルトダウンではない」と言い張った当時の菅直人政権の官房長官の姿が思い出される。
コロナ禍の1年を経験し、3.11当時の「社会」を振り返ると多くを失ったが今なお切に生きる人たちがいることを通説に感じる。そして、「現在」との比較をどうしてもしてしまう。一言で言えば、復旧・復興に向け社会が災害に向かうという緊張感のある「一体感」があった。しかし、現在はどうかと言えば、緊急事態制限発出や延長に関し、政府と東京都との間での駆け引きを見るにつけ、東日本大震災当時の住民本位である行政とのあまりに大きな違いに唖然とする。以降、防災については多くの面で学びそして進化して来た。しかし、「政治」は逆に退化し続けている。
亡くなった作詞家阿久悠さんは、晩年「昭和とともに終わったのは歌謡曲ではなく、実は、人間の心ではないかと気がついた」と語り、「心が無いとわかってしまうと、とても恐くて、新しいモラルや生き方を歌い上げることはできない」と歌づくりを断念した。しかし、3.11後の光景は痛みとともに、「絆」というキーワードに表される共助の光景をも見せてくれた。大津波は自助できるものを大きく超えたものであった。更に、頼りにすべき行政機関も津波で持ち去られ、残るは生き残った人々の共助だけとなった。多くの場合こうした災害後には略奪などが横行するのだが、日本の場合は互いに助け合う共助へと向かい、世界中から賞讃された。阿久悠さんは「心が無い」時代に歌うことはできないとしたが、実は東北には心はあったのだ。今一度10年前の東日本大震災の原点に戻らなければならない。
忌野清志郎が歌う「雨あがりの夜空に」の歌詞に次のようなフレーズがある。
・・・・・・・・・・・・
こんな夜におまえに乗れないなんて
こんな夜に発車でないなんて
こんなこといつまでも長くは続かない
・・・・・・・
Oh雨上がりの夜空にかがやく
Woo雲の切れ間に
散りばめたダイヤモンド
・・・・・・・・・・
そして、忌野清志郎は私たちに「どうしたんだHey Hey Baby」と投げかける。乱暴だが、とてつもなく優しい。「切に生きる」人たちへ、そんな応援歌が待たれている。今なお、戦いは続いているということだ。(続く)
追記 テーマから言うと大津波などの画像の方がわかりやすいが、やはり胸が苦しくなり、好きな忌野清志郎の応援歌の写真を使うこととした。
タグ :東日本大震
失われた30年nの意味
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
Posted by ヒット商品応援団 at 13:27│Comments(0)
│新市場創造
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。