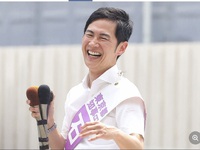2019年09月11日
混乱税率の10月を迎える
ヒット商品応援団日記No746(毎週更新) 2019.9.11.
この1ヶ月ほどブログの更新が途絶えていたが、あと数日ほどで未来塾で今後の新しいマーケティングの発想をレポートする予定である。ただその前に10月に導入される消費増税は予測以上の混乱が待っている。この混乱をどう顧客に対し応えていくか書いてみたい。
半年ほど前にも今回の消費増税の問題点を指摘した。軽減税率とキャッシュレス化推進のためのポイント還元制度である。当たり前のことだが、税は公平さとわかりやすさが大前提となる。今回の消費増税はこの「わかりやすさ」が決定的に欠けている。いや、欠けているどころか税の負担感を少なくする「軽減」がこの「わかりにくさ」=混乱を招いているということである。更にキャッシュレス化を推進するために行うポイント還元もこのわかりにくさを増幅させている。こうしたわかりにくさを持ち込まないために、特に飲食業の場合店頭での店内飲食かテイクアウトかを確認することが推奨されているが、こんな手間のかかるオペレーションを避ける飲食店も当然出てきている。
まずコンビニやスーパーにおけっる店内飲食の場合、「店内飲食の場合はお申し出ください」といった掲示をしていれば、店員が客に店内で食べるかどうかの確認は不要。つまり、レジでは自己申告に任せることとなる。当然、顧客は店内で食べてもテイクアウトにおける税率8%ということとなる。以前指摘をしたように、想定される顧客とのトラブルを避けるためである。
例えば、牛丼のすき家の場合店内飲食の価格を値下げし、テイクアウトでも店内でも同一価格で提供すると発表されている。一方、吉野家やミスタードーナツは店内飲食は10%、テイクアウトは8%という税率価格を実施するという。また、ケンタッキーフライドチキン、マクドナルド、ガストの場合はすき家と同様の同一価格にするという。
こうした価格設定もさることながら、肝心要の軽減税率対応の「レジ」が不足し、10月実施に間に合わないという。政府は新レジ購入が契約されている場合は支援すると発表されているが、問題は新レジの初期設定もさることながら、レジへの商品登録の大変さである。
どんな小さな店においても最低でも数十、数百もの商品・メニュー登録が必要となる。それは商品内容の詳細を確認しながらの作業である。例えば、年末のおせちの場合「包装箱」の想定金額が一定以上占めている場合、税率は8%ではなく10%となる。何故、こうした軽減税率の受け止め方に違いが出てくるのか、その理由は経営の考え方にある。すき家の場合はわかりやすさと共に店内飲食の比率が大きく、こうした顧客を維持することが主眼となっているからである。つまり、出店立地の違いがこうした店内飲食、テイクアウトの同一価格になったということである。
さてこうした軽減税率の受け止め方の違いはどのような消費心理を招くことになるかという問題である。まず考えなければならない第一は、8%と10%の2%差を消費者はどう受け止めるかである。私は多くの商店街、特に活力溢れる中小の商店で構成される商店街を多く見てきた。江東区の砂町銀座商店街、ハマのアメ横興福寺松原商店街、吉祥寺サンロード・ダイヤ街、谷中銀座商店街、地蔵通り商店街、上野アメ横、・・・・・・・それぞれ特徴ある商いをしている商店街ゅであるが、推測するに軽減税率対応の新レジを準備している商店は極めて少ないと思う。政府の補助金を活用できるが、それでも数十万単位以上の経費がかかることとなる。
初めて砂町銀座商店街を訪れた時、ちょうど8%の消費税導入実地直後であったが、従来の内税方式で現金決済の商店でほとんどであったが、勿論増税分近くの値上げをしましたと店主は話してくれたが、増税による影響はほとんどなかったという。その理由はただ一つ、顧客との間に「会話」があるという一点である。これは単なる原理原則を言っているのではない。複雑でわかりにくい「税」による混乱は店側との生の会話によってのみ理解されるであろう。
こうした対話ができないチェーン店の場合はすき家のように同一価格にする、つまり値引きしてでもわかりやすさを優先する方法を選んだということである。こうした値引きはマクドナルド(一部商品は10円アップ)などでも同様でである。
しかもキャッシュレス化のための中小商店の申請が8月末時点では想定されている商店数の約四分の一程度であると言われている。消費者にとってポイント還元できるのか否か、更にはどの電子マネーの決済であるか、店や商品を選択する前に判断しなければならない。極論ではあるが、中小商店利用の場合自身が使いたいと考えている電子マネーに該当する店はかなり少ないということだ。つまり、キャッシュレスという便利なようで便利ではない現実を迎えるといことだ。そうしたことを含め、店頭での表示が重要となる。キャッシュレス申請店の場合、政府からポスターが提供されるが、そのことより重要なことは、今一度内税・外税を明確にし、顧客の側の選択しやすさに答えることが必要である。すき家のように値下げして店内飲食とテイクアウトを同一価格にするという「わかりやすさ」の表示のことである。
こうしてブログを書いている最中に吉野家はキャッシュレス決済におけるポイント還元には参加しないとのニュースが入ってきた。理由はシステム改修が間に合わなかったことによるとの発表であった。一応、自社ポイントなどを使った還元策を別途用意する予定であるとも。これで日本マクドナルドの7割のFC店がこのポイント還元策に参加することになる予定であるが、他の大手チェーン店であるすき家、ガスト、ケンタッキーなどは参加しないこととなり、つまり、キャッシュレス化はほとんど進まなくなったということである。あれもこれもとこの機に盛り込み、税の基本である公平さとわかりやすさが導入前から破綻してしまっているということである。
顧客接点である店も顧客も混乱混迷の10月を迎えることとなる。こうした状況にあって駆け込み需要など起こりようが無いということでもある。ただ、あと1週間ほど経過したらわかると思うが、アマゾンや楽天などネット通販への注文が一斉に出てくるであろう。ただ、出荷時点での税率適用のため、早めに注文することになるかと思う。TV報道のように百貨店における冬物のブランドコートなどを駆け込み購入していると言われるが、限定的で駆け込み需要では無い。
起こるのは戸惑いと混乱の10月になるということだ。(続く)
この1ヶ月ほどブログの更新が途絶えていたが、あと数日ほどで未来塾で今後の新しいマーケティングの発想をレポートする予定である。ただその前に10月に導入される消費増税は予測以上の混乱が待っている。この混乱をどう顧客に対し応えていくか書いてみたい。
半年ほど前にも今回の消費増税の問題点を指摘した。軽減税率とキャッシュレス化推進のためのポイント還元制度である。当たり前のことだが、税は公平さとわかりやすさが大前提となる。今回の消費増税はこの「わかりやすさ」が決定的に欠けている。いや、欠けているどころか税の負担感を少なくする「軽減」がこの「わかりにくさ」=混乱を招いているということである。更にキャッシュレス化を推進するために行うポイント還元もこのわかりにくさを増幅させている。こうしたわかりにくさを持ち込まないために、特に飲食業の場合店頭での店内飲食かテイクアウトかを確認することが推奨されているが、こんな手間のかかるオペレーションを避ける飲食店も当然出てきている。
まずコンビニやスーパーにおけっる店内飲食の場合、「店内飲食の場合はお申し出ください」といった掲示をしていれば、店員が客に店内で食べるかどうかの確認は不要。つまり、レジでは自己申告に任せることとなる。当然、顧客は店内で食べてもテイクアウトにおける税率8%ということとなる。以前指摘をしたように、想定される顧客とのトラブルを避けるためである。
例えば、牛丼のすき家の場合店内飲食の価格を値下げし、テイクアウトでも店内でも同一価格で提供すると発表されている。一方、吉野家やミスタードーナツは店内飲食は10%、テイクアウトは8%という税率価格を実施するという。また、ケンタッキーフライドチキン、マクドナルド、ガストの場合はすき家と同様の同一価格にするという。
こうした価格設定もさることながら、肝心要の軽減税率対応の「レジ」が不足し、10月実施に間に合わないという。政府は新レジ購入が契約されている場合は支援すると発表されているが、問題は新レジの初期設定もさることながら、レジへの商品登録の大変さである。
どんな小さな店においても最低でも数十、数百もの商品・メニュー登録が必要となる。それは商品内容の詳細を確認しながらの作業である。例えば、年末のおせちの場合「包装箱」の想定金額が一定以上占めている場合、税率は8%ではなく10%となる。何故、こうした軽減税率の受け止め方に違いが出てくるのか、その理由は経営の考え方にある。すき家の場合はわかりやすさと共に店内飲食の比率が大きく、こうした顧客を維持することが主眼となっているからである。つまり、出店立地の違いがこうした店内飲食、テイクアウトの同一価格になったということである。
さてこうした軽減税率の受け止め方の違いはどのような消費心理を招くことになるかという問題である。まず考えなければならない第一は、8%と10%の2%差を消費者はどう受け止めるかである。私は多くの商店街、特に活力溢れる中小の商店で構成される商店街を多く見てきた。江東区の砂町銀座商店街、ハマのアメ横興福寺松原商店街、吉祥寺サンロード・ダイヤ街、谷中銀座商店街、地蔵通り商店街、上野アメ横、・・・・・・・それぞれ特徴ある商いをしている商店街ゅであるが、推測するに軽減税率対応の新レジを準備している商店は極めて少ないと思う。政府の補助金を活用できるが、それでも数十万単位以上の経費がかかることとなる。
初めて砂町銀座商店街を訪れた時、ちょうど8%の消費税導入実地直後であったが、従来の内税方式で現金決済の商店でほとんどであったが、勿論増税分近くの値上げをしましたと店主は話してくれたが、増税による影響はほとんどなかったという。その理由はただ一つ、顧客との間に「会話」があるという一点である。これは単なる原理原則を言っているのではない。複雑でわかりにくい「税」による混乱は店側との生の会話によってのみ理解されるであろう。
こうした対話ができないチェーン店の場合はすき家のように同一価格にする、つまり値引きしてでもわかりやすさを優先する方法を選んだということである。こうした値引きはマクドナルド(一部商品は10円アップ)などでも同様でである。
しかもキャッシュレス化のための中小商店の申請が8月末時点では想定されている商店数の約四分の一程度であると言われている。消費者にとってポイント還元できるのか否か、更にはどの電子マネーの決済であるか、店や商品を選択する前に判断しなければならない。極論ではあるが、中小商店利用の場合自身が使いたいと考えている電子マネーに該当する店はかなり少ないということだ。つまり、キャッシュレスという便利なようで便利ではない現実を迎えるといことだ。そうしたことを含め、店頭での表示が重要となる。キャッシュレス申請店の場合、政府からポスターが提供されるが、そのことより重要なことは、今一度内税・外税を明確にし、顧客の側の選択しやすさに答えることが必要である。すき家のように値下げして店内飲食とテイクアウトを同一価格にするという「わかりやすさ」の表示のことである。
こうしてブログを書いている最中に吉野家はキャッシュレス決済におけるポイント還元には参加しないとのニュースが入ってきた。理由はシステム改修が間に合わなかったことによるとの発表であった。一応、自社ポイントなどを使った還元策を別途用意する予定であるとも。これで日本マクドナルドの7割のFC店がこのポイント還元策に参加することになる予定であるが、他の大手チェーン店であるすき家、ガスト、ケンタッキーなどは参加しないこととなり、つまり、キャッシュレス化はほとんど進まなくなったということである。あれもこれもとこの機に盛り込み、税の基本である公平さとわかりやすさが導入前から破綻してしまっているということである。
顧客接点である店も顧客も混乱混迷の10月を迎えることとなる。こうした状況にあって駆け込み需要など起こりようが無いということでもある。ただ、あと1週間ほど経過したらわかると思うが、アマゾンや楽天などネット通販への注文が一斉に出てくるであろう。ただ、出荷時点での税率適用のため、早めに注文することになるかと思う。TV報道のように百貨店における冬物のブランドコートなどを駆け込み購入していると言われるが、限定的で駆け込み需要では無い。
起こるのは戸惑いと混乱の10月になるということだ。(続く)
タグ :消費増税
失われた30年nの意味
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)前半
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
Posted by ヒット商品応援団 at 13:17│Comments(0)
│新市場創造
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。